イギリスでは新自由主義的な転換が最も早く行われたがゆえに、新自由主義の限界もいち早く明らかになった。新自由主義的な改革とは玉葱の皮むきのようなものであり、「官から民へ」を推し進めた終着点で、政府が何をするのかについては何の構想もない。新自由主義はその意味で政治の否定なのである。
「ブレア時代のイギリス」 山口二郎
イギリスは二大政党制の国であるが、この十年数年は労働党の政権が続いていた。
ところで、労働党政権を誕生させ、戦後最長の同党の政権を率いたトニー・ブレアは、いろんな意味で、小泉元首相と似ている。
党内改革を大胆に実行する手管。世論の風を一手に引き受けるメディア戦略。
ブレアにはスピンドクター(情報操作の専門家)を活用する手法(飯島秘書官の存在が非常に似ている)。
(ブレアのマスコミ戦略や情報戦略の内幕については「仁義なき英国タブロイド伝説 山本浩
」が面白く取り上げていて興味深い内容となっている)
そしてさらに何よりも似ているのは、個人的で人格的な魅力を最大限に発揮した強いリーダーシップスタイルである。これが世論を味方にし、改革を可能にした秘密である。
しかし、もちろんブレアと小泉は政治家として目指したところは全く違う。
さらに政治的背景として、もっとも違うのは、ブレアがサッチャリズムという新自由主義的な政策が綻びを見せ、全く予想したとおりに限界を迎えた後に現れたことだ。
ブレアは、新自由主義の目論見と福祉国家のコンセプトをなんとかバランスよく調合し、新しいイギリスの指針を処方したのである。すなわち「第三の道」である。
小泉は新自由主義の入り口を提示したに過ぎない。
イギリスは第二次世界大戦後、すぐに労働党政権となり、「ゆりかごから墓場まで」と言われる福祉国家政策を取り出した。
公営住宅、鉄道の国有化、社会保障制度の推進、医療費の無料化などなど。社会民主主義的な政策は、その後も70年代のサッチャーの時代まで引き継がれる。
これが否定されるのはサッチャーの時代である。
もともと「新自由主義」と呼ばれる政策は、「サッチャリズム」という名の下に始まった。
小さな政府による、市場経済を前提とした民営化、財政支出によるケインズ流の財政政策の放棄など。
70年代には、イギリスは没落していたのだ。「イギリス病」は、競争力を失った企業と怠惰な労働者を生み出した福祉国家政策が元凶とされていた。
本エントリの「ブレア時代のイギリス」の著者は、森嶋通夫著「サッチャー時代のイギリス―その政治、経済、教育」の続編として読まれるべき作品だ。その「サッチャー時代のイギリス」の作者は、、このサッチャーによる利潤原理による市場の見えざる力を社会に、より大胆に導入する手法を、「逆シュンペーター過程」と呼んでいる。
シュンペーターは、資本主義は放っておけば、資本の独占により「社会主義化/全体主義化」せざるを得ないというマルクスとは違ったスタンスのアプローチで、資本主義がこともあろうに「社会主義化」して自滅すると結論づけた。資本主義は癌で死ぬのではなく、ノイローゼで死ぬというわけである。これは、主に変化を失った社会の中で、民主主義的な仕組みをとらざるを得ない資本主義の市場原理は、かえって経済的な勝者に活力を失わさせていくという逆説的な論である。
もっともサッチャーはシュンペーターを本当に意識していたのかもわからないし、むしろ当時すでに気鋭の経営学者となっていたP.F.ドラッガーの影響のほうが強かったかも知れない。もちろん、サッチャー自身は当の本人に軽蔑されていたというハイエクの影響をもちろん忘れることはできない。
なにはともあれ、資抗するサッチャーは、「ビクトリア朝時代に帰れ」とのスローガンで、資本の活発な動きを促進するために、様々な手立てをとり始めた。
そして、利潤原理で勝者と敗者が現れることは当たりまえのこととして受け止め、「くやしかったら、がんばりなさい」という論理を押し立てた。
その結果、民営化、規制緩和、減税、これらが進み、財政削減による小さな政府へと展開される一方、イギリスでは失業者は増えていき、社会的不満は鬱屈していった。
その一方で海外からの投資は増え、製造業から金融をはじめとするサービス業へとイギリスの産業構造は劇的に変化している。現在のイギリス金融市場の活性化はここがひとつのターニングポイントとなっていることはいうまでもない。
サッチャーからメージャーに変わっても、新自由主義的政策を保持する保守党は足掛け18年政権を担当しつづけた。
その間に問題は膨らんでいた。貧富の差は広がり、医療や教育では公的サービスの荒廃が限界線まで達していた。92年の金融危機をきっかけに、保守党の政策に批判が高まり、そしてブレアが登場する。
ブレアは、労働党の改革に着手したうえで、サッチャリズム政策の修正にとりかかった。
そのとき、労働党はすでに数々の伝統的な社会主義的政策やケインズ流の財政政策を放棄している。例えば、生産手段の国有化は労働党の綱領からブレアによって削除されているし、福祉国家を維持するための政府による租税財源の確保、すなわち高累進課税や法人税を抑えて海外からの投資を導くスタイルは、サッチャー時代のものを引き継いだものだ。
そのうえで、教育や雇用プログラムを改革し、サッチャー時代に荒廃していた医療改革をするなど、公共サービスを新しい手法で立て直すことを行った。
「われわれの目標は、人々が市場の圧力によってなすがままにされるのではなく、市場の中で、自立的に活動できる人間を育成することである。」
ブレアの手法はある程度成功しているのは、イギリスの現在の好況と社会サービスの復活というテーマが著しく改善しているところからわかる。
おそらく、新自由主義的な経済政策や政治改革のプログラムを行う国家は、おおかれ少なかれ、このような社会主義的-福祉国家的-ケインズ主義的な処方を取らざるを得ない局面が出てくるはずである。
中南米の社会主義化の動きも、このような経済のグローバリゼーションに抗するひとつの揺り戻しと考えることが出来る。
世界経済は統合の方向に急速と進んでいる。IMF-WTO-世界銀行というトライアングルで形成された国際市場の枠組みに、今ではどこの国家であっても、それが例えばウーゴ・チャベスのような「新しい社会主義者」であっても、逆らうことは出来ない。市場原理を導入することということはは、すなわち統合された世界経済のステージに立つことを意味する。それに対するショックを少なくするために、国家は「社会的排除」されてきた弱者を手当てすることぐらいしか出来ない。
ときどき、オールドファッションな経済ブロックをつくって自国内の再配分の仕組みをなんとか維持しようとする試みがはじまり、それがあたかも最新の試みのように喧伝されるかもしれないが。
ここで社会民主主義は大きな難問にぶつかる。グローバルな資本主義とどのように折り合いをつけるのかという問いである。
(中略)
イギリスでニューレーバー(ブレアの新しい労働党の戦略)が目指したのは、グローバル資本主義という現実を受け入れたうえで、リスクの社会化や平等を最大限追求するというプロジェクトであった。
自由主義はどこまで行くことが出来るのか、国家は市場の結果(豊かな国の市民が貧しい国の市民に負担させているもの)をどの程度是正すべきなのか、あるいは環境などを射程にすえた調整をどこまで行うべきか、といった問題を議論するのは当然のことである。
マーティン・ウルフ
しかし、問題はそういうことなのか?
「ブレア時代のイギリス」の著者は、ブレア流の「社会民主主義」の実験が、資本主義を是正するのではなく、単に資本主義に人間を慣れさせることに過ぎないのでないかという懸念を示す。
すでに生存手段の生産というような実態経済が全く意味をなさないような金融取引が世界を駆け巡り、世界中の市場が統合されるような時代・・・・ある意味でマルクスやシュンペーターが預言したように資本主義が資本主義を崩壊させるような事態が・・・世界規模で到来するときが来るのではないか。そのとき、洪水に対してわれわれは世界規模で自らを救うための船を用意することは出来るのか。
そして、すでに現時点で絶対的窮乏化にさいなまされている世界中の人々が、自らの救済のために、何か決定的に違うアクションに陥ることはないのか。経済が傾くときに、世界は何度も最悪の選択を選びつづけてきた。
ブレアは、イラク政策の失敗(というか、強引な参戦)を問われ、これが最後まで響いて政権を手放した。が、この問題がなかったら今でも彼は政権を維持していたに違いない。
おそらく、日本にもブレアが試みたものと同じような揺り戻しの時がやってくるだろう。
しかし、まだその先を進めるための想像力を私たちはもっていない。
イギリスの選択は、そのまま数十年遅れて日本にやってきた。だから、日本経済と政治の今後を占うとすれば、まずはサッチャーからブレアへの遷移をチェックするとわかりやすい。
なんでもかんでも小さな政府・民営化・バラマキ是正などというキーワードがくれば正しいと思っている単純なメディアマジックにひっかかっている人は多少とも、イギリスの70年代から現在までの政治史を把握してよいのではないかと思う。
日本人はこういう潮流にキャッチアップする術に長けている反面、調子に乗りすぎることも多い。「バスに乗り遅れるな」方式の思考遮断にトクなどひとつもない。
※初出:2007年10月22日
そうして、その3年後に民主党政権になるわけですね。民主党政権下のはじめての選挙があと一カ月後です(2010.6.9)
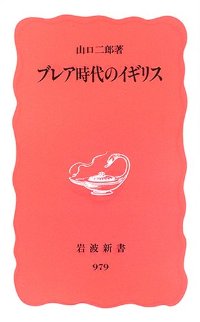

コメント