『美と共同体と東大闘争』 三島由紀夫vs東大全共闘
『太陽と鉄』 三島由紀夫
大阪の心斎橋、アメ村のあたりをうろちょろしていると、雑貨屋と本屋と半々になっている面白い店を発見する。
しばらく時間をつぶしていたのだが、フェラクティの伝記やらにまじって三島由紀夫の特集コーナーが平積みされていて、そこでフューチャーされていたのが、三島の全共闘との討論の文庫本。
三島の評論ものなどで、断片的にしか読んでなかったので購入。
ついでに、『太陽と鉄』。
これは表題作は随分昔に読んでいるのだが、そこに並収されている『私の遍歴時代』のために買い込む。
全共闘討論は、ドキュメントとして面白い。当時の雰囲気を如実に伝えるちょっとしたエピソードがむしろ語られている内容より面白いぐらいだ。
三島 ここには灰皿ないんですか、煙草も飲めないんですか?
全共闘A いや、どうぞ床の方で結構です。
三島 ああ、床・・・・うん。
などという件や、全共闘学生同士のウチワモメや壇下からのヤジなどは、ちょっとした芝居じみていてなかなかにスリリングである
基本的に、討論は幾つかのテーマに収斂されていくのだが、特にそれが身のあるものかといえば、どうだろう。表題は『美と共同体と東大闘争』とあるが、そのタイトルにふさわしい展開の議論はおこなわれない。
この本が発売当初ベストセラーになってから、しばらく埋もれていた(ように見える)のはそういうところからなのだろう。
特に本の前半ページを占める自然と事物の形而上学的議論はひたすら退屈である。
この本の中で行われた討論の中で、唯一学生らしく直截に三島のふところに差し出された危険はひとつだけ。
全共闘Hと名前がついた人間からの発言。
この発言は非常に面白い三島の反応をひきだしている。
以下、抜粋。
全共闘H 三島がね、今「英霊の声」以来、天皇についていろいろ書いているし、感情を書き散らしていると。しかし、ぼくが思うに、今天皇がいないからこそ三島はああいうことを書いているのであって、今天皇がいたらああいうことを書くはずがない。
つまり非現存の存在だからこそ、三島に言わせれば、至高としての、同時に至禁としての美が存在すると。(中略)
それなのに、なぜ三島が自衛隊に一日入隊なんかして、あるいはヘンな右翼のまねごとなんかするのか。
三島が美を追う物書きであれば、美は美の中で簡潔するのだから、ヘンな甘っちょろい、ぐだぐたした行動なんかしないで、三島がその美の中にとじこもらないで、行動に出てくる時、天皇としての美が、実は共同幻想として、共同規範として、非常にみっともないものになってしまうと。
そのへんに三島さんの欠点があるのではないかとはぼくは思うわけです。
この発言に対して、三島は明確な答えを最後まで出さない。
もちろん、それは質問された本人が答えられる性質のものでないから、韜晦するのである
三島の政治的活動を茶番として退けるのは容易い。
全共闘Hのように、そこを「欠点」として指摘するのも簡単だし、石原慎太郎のように(「三島由紀夫の日蝕」)徹底的に茶化して逆説的な悲劇、つまり喜劇仕立てにつづるのもありえる態度だろう。
しかし、そこにとどめてしまっては、三島由紀夫という名にまつわることとなった異様な物語のパワーの背景を読み取ることは出来ないし、さらにはそれを解体することもできない。
『太陽と鉄』は、発表当時から酷評を与えられ続けた作品である。
三島の緊密で、それゆえに芝居ががった文体のドラマが、止め処もなく現実の方へとなだれおちていき、ほとんどジョークではないかとも思える滑稽な詩的文体が、下世話な50年代末の時代光景に汚されていく。
全共闘Hがいう、無粋に近い指摘はその意味で確かに的を得ている。
大江健三郎の「セブンティーン」そして「政治少年死す」に至る右翼ものの問題作は、
もう「太陽と鉄」の忠実なパロディではないかと思わせる。まさに突っ込みどころ満載。
(最近この「政治少年死す」をやっと読むことが出来た。アングラ雑誌が強行突破で雑誌のコピーを全文掲載したものだ。こいつらは偉いと思う。次は、石原慎太郎の「処刑教室」を掲載してくれ!)
さて、全共闘Hの発言に対して、韜晦を巡らす三島に対して、激高する他の全共闘学生に対して三島は、それ自体マジメに答えているのがわからぬのか、と逆ギレで返す。
韜晦はここでは肯定である。そして、だからこそ同時に当の本人が答えるべき問題ではないのでもある。
三島の欠点は、それ自体が三島そのものの存在の意義なのであるから、それを否定されても、普通はああそうですか、としか答えようがない。
三島は、この学生の質問に対して、2つの有名な発言をもって返す。
ひとつは、例のあれだ。きみたちが「天皇」と一言いえば、オレはきみらにつく、というもの。
もうひとつは、三島の天皇観。
三島は古事記を引き合いに出して、極めて独自の天皇観を語るが、それは「架空の、それゆえに至禁の天皇」
という全共闘Hの発言を肯定しているようにしか読めない。
ちなみに、前の「天皇と口にすれば・・・」の方については、こういう面白い発言を「私の遍歴時代」に三島が書いているのがむしろ興味深い。
これも有名なエピソードであるが、学生の自分、太宰治に対して「あなたの作品は嫌いなんです」と三島がテロリスト風情で宴席上で言いに行ったときのことを回想してのものである。
「あなたの文学は嫌いです」と面と向かって言われた心持ちは察しがつく。私自身も何度かそういう目に会うようになったからである。(中略)
こういう文学上の刺客に会うのは文学者の宿命のようなものだ。もちろん、私はこんな青年を愛さない。
こんな青臭さの全部をゆるさない。私は大人っぽく笑ってすりぬけてるかきこえないふりをするだろう。
ただ、私と太宰氏の違いは、ひいては二人の文学のちがいは、私は金輪際、「こうしてきているのだから、好きなんだ」などとは言わないだろうことである。
実際、三島は全共闘hに対して韜晦というテクニックで、何も言わない。
そして、逆説的なジョークで切り抜ける。曰く、「天皇とひとこと君等が口にすれば・・・」である。
しかしぼくには、これは宴席の太宰がテロリスト三島に言ったコトバ「そんなこといったって、こうしてきているのだから好きなんだろう・・・」とさして変わらない態度だとも思うのだが。
三島の本質は、美的世界を外部に延長する行動そのもの、それを叙述することだ。
少年期と青年期のナルシシズムは、自分のために何をでも利用する。世界の滅亡でも利用する。鏡は大きければ大きいほどいい。二十歳の私は、自分を何とでも夢想することが出来た。
金閣寺に放火した少年僧の悪意に満ちた自己延長の欲望。鏡に映すのは自己である。
自己を投影する対象物は、大きければ大きいほどスリリングであり性的に充実することができる。
三島は、このような認識が20代中盤で昇華されたのだと「私の遍歴時代」で書く連ねるが、それはアリバイ工作に過ぎない。
三島の自己投影のための仕掛けづくりは、いちだんと手が込んだものとなっただけで、
単に色の違う裏返したシーツにくるまって横たわっているだけなのである。
私に余分なものといえば、明らかに感受性であり、私にかけているものといえば何か、肉体的な存在感とでもいうべきものであった。すでに私はただの冷たい知性を
軽蔑することをおぼえていたから、一個の彫像のように、疑いようのない肉体的な存在を持った知性しか認めず、そういうものしか欲しいと思わなかった。それを得るには、
洞穴のような書斎や研究室にとじこもっていてはだめで、どうしても太陽の媒介が要るのであった。
三島が折に触れ、書き連ねる「肉体」や「太陽」というコトバにハメられるのは賢明な態度ではない。
また、そこにうさんくささを嗅ぎつけて、ただ遠ざけるのも、これも賢明とはいえない。
三島がいう「肉体」や「太陽」というコトバに、祭りの日に神輿をかついでその喧騒と興奮の中に見た青空や、自衛隊のF104の体験飛行に感じた性的フレーズを重ね合わせるのは、三島の手の込んだトリックに幻惑されてしまうだけなのである。
(大江健三郎の「性的人間」そして右翼の脅迫と出版社への暴力的圧力により未だ日の目を見ることができない「政治少年死す」は、そのトリックを大げさに反復し、パロディとして茶化した。そしてだからこそ、彼らの逆鱗に触れる破壊力があったのである。)
美的世界を外部に延長すること。
そして、そのスリル。
それは露出癖のある性的倒錯者とあまり変わらない。
三島が、いくらそれが、自らの感受性の過剰の嫌悪から招いたたものと膨大にあちらこちらに書いたとしても、
残念ながらそれに説得力は感じられない。
三島の書くところによれば、禁色第一部と第二部の間、つまり彼が二十六歳の時、ひとつの転換が行われたと書いている。三島が自己をマスメディアに露出させ、様々な痴態に近いスキャンダラスなネタを披露しはじめたのは恐らくこのへんがきっかけになっているはずだ。(作品の時代考証してませんけど・・・)
政治は、そのためのひとつの手段である。
天皇もその手段のひとつである。手段だから、それは架空の天皇でかまわないし、実現など出来るはずもない
古代王権の長の姿を夢想するのでも全く構わない。
三島はそういう意味で、「政治」などは全く信じていないのである。ただ単に、それは自分自身を投影する鏡であればよいのだ。
全共闘に対して、天皇のひとことで連帯することを冗談まじりながら述べることの出来る背景はそこにあるし、政治論理としてひとつも有効なものを示すことをしなかった彼の政治団体の理由もそこにある。
三島にとって、「政治なんてその程度のもの」なのである。
三島の文学が傑出しているのは、その倒錯である。
そして、その倒錯の論理を三島はエロティックに外部世界に延長を開始した。
延長を開始する三島にとって、美の論理をテキストの中で完結させることなど
もうどうでもいいことであり、自らをその論理に当てはめて振舞うことが重要になった。
滑稽な三島の政治少年としての活動とスキャンダラスなマスコミ露出は、それが原因である。
三島のテキストに秘められた可能性は、その倒錯の論理そのものなのであり、政治活動は本来
どうでもいいことだ。変質のターニングポイントを見失うのは、危険である。
三島をあざ笑う石原慎太郎のテキストは、同時に三島の倒錯の論理を無自覚にひきづっている
だけにしか見えないのだが、これもそのターニングポイントがどのように訪れたのかを
理解してない人間だけが行えるものだ。三島の政治活動を笑うことは出来ても、文学者としての、ひとつの「誠実」をぼくは決して笑うことは出来ない。
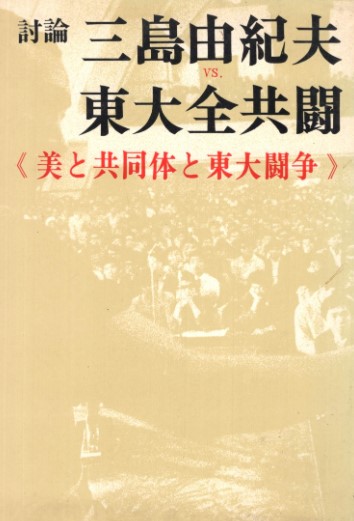
コメント