
小津の「夏三部作」つまり『晩春』『東京物語』『麦秋』の名声に比べれば、それに続いた一連のカラー作品の後世の評価はさして高くない。
「秋三部作」と呼ばれる『秋日和』『小早川家の秋』『秋刀魚の味』も、興行収入が良かった割には、いまひとつだ。
「僕は豆腐屋なんだから、ガラッと変わったものを注文されてもダメだよ。油揚とかガンモドキに類したものはいいけど、カツ丼を作れと言われてたった無理だよ。がんもどきや油揚げは作るが、西洋料理は作らないよ」と嘯いていたのは、一種自分のつくりあげてきたスタイルに対する自信の表れだろう。
戦前の小津本人曰く「オレもヌーヴェルヴァーグだった」時代から、喜八ものの小市民の人情モノを経て、さらに戦乱期の中の傑作『戸田家の兄妹』、さらには「夏三部作」の決定的な成功で、小津はまさしく松竹に君臨する巨匠だった。
その小津も、あたかも自分の撮っていた作品の主人公のように、時代の行く末に静かに流されていくようになる。秋三部作の中でも決定的な作品『東京物語』から3年間、小津は映画を撮らず、再開した『早春』の年に、日活から『太陽の季節』が公開。そして、松竹にも続々と「松竹ヌーヴェルヴァーグ」と呼ばれる若手が監督としてデビューしはじめる。
その頃に小津はカラー作品を手掛け始める。ここから小津の作品にポップな彩りが感じられ始めるようになる。
この部分を評する人たちはあまり評価しないのである。自分はむしろ小津のカラー作品が皆好きだ。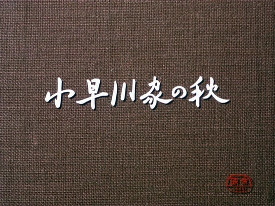
本作品『小早川家の秋』は、小津が東宝に出ていって撮った作品。新珠三千代、宝田明、小林桂樹、団令子、森繁久彌、白川由美、藤木悠の東宝のオールスター作品となっている。そしてとどめは中村鴈治郎。ストーリーは鴈治郎の老いと死をめぐる顛末が、滑稽かつグロテスクに綴られるものだ。
森繁久彌は「松竹のヘボ役者なら演技は出来ないが、オレならアドリブもできる」というようなことを言って、小津の逆鱗に触れたというエピソードがある。結局はあの森繁が、縮こまった演技でポツポツとストーリーの要所に出てくる程度でおさまっているのが、なにやらおかしく感じる。
小津のあのカメラの構図に、カラーの色がまぶしく、これだけでもよろしい感じである。
映画全体に繊細な色へのこだわりがある。
ピエロように生き返ってはまた死んでいく中村鴈治郎も印象的だ。逆にいえば、この人が強く作用しすぎて、ラストの葬送シーンのあたりが唐突に感じられるのかもしれない。京都の愛人が、あっけからんと死に対するあたりといい、ほとんどシュールである。ここには「夏三部作」の言葉にならない無常感と表裏一体をなすようなあっけらからんとした死生観がある。
司葉子と原節子のラストシーンのあたりでバランスをとろうとしたのかもしれないが、これはやはり「夏三部作」を評価する人あたりに評判が悪いのは当たり前だろう。どちらかといえば、この作品はブラックコメディに類するべき作品である。
この作品『小早川家の秋』のあと、『秋刀魚の味』を撮って小津は死去。
死の直前に結局はクランクアップしなかった『大根と人参』を、病床の小津は「がんもどき」と呼んでいたらしい。
油がまわったがんもどきと評した作品が、どんなものになるはずだったのかはわからないが、そうすると、この作品『小早川家の秋』は、がんもどきほどには豆腐から離れたものでもないけれど、油揚げくらいの作品なのかもしれない。
確かに、これは湯に通したり、またはそのままで食べるのにはむいてなさそうだ。
煮しめて食べるか、味噌汁にでもいれるか。
銀座シネパトス特集「魂なる輝き 映画女優・原節子」にて
この作品は原節子が最後に小津と組んだ作品。そして原節子は小津の死から女優を引退する。そればかりか、小津の葬儀の後、公の場に一度も姿を見せていない。
「小早川家の秋」 小津の油揚げ
 映画評
映画評 この記事は約3分で読めます。
コメント