
クレイマー、クレイマー – goo 映画
若かりし日の吉本隆明(吉本ばななの父ちゃんの偉いひと)が、当時の文学青年のあこがれの存在であった太宰治のところを尋ねたときのエピソードが、ずっとひっかかっていて忘れられない。
-「太宰さん、いま重くないですか」と聞いてみた。「そりゃあ、重いさ。だけど、お前、男性の本質は何か知っているか」と言うから、「いや、全然わかいません」と答えたら、「それはマザーシップということだよ」って言ったんです。 「貧困の思想」-
もしや太宰が思い悩んだようにやってきた学生さんにジョークのひとつとしていったことかもしれないこの言葉の意味をどうとるかは大変微妙なところではあります。
げんに太宰がそのセリフの後にかぶせたのは「だから、おまえさんその汚いヒゲを剃れ」というものだったらしいですし(笑)
なお、この言葉を実直に受け取ったかどうかはわかりませんが、吉本家では病弱な妻に変わって、執筆の傍らに家事や炊事をしていたのは吉本隆明でした。ご近所では買い物かご下げて近所に買い物をする吉本先生の姿は有名だったらしい。ここまでの話が、まさか太宰の影響とは思いませんけれども。
ところが、その吉本センセには、「食を語る」という本があるのですが、これに出てくる料理がこれまたとてもおいしそうな料理には思えないんですね。やっぱり男のマザーシップはトンチンカンになってしまいますよ。うん、しかしまあこれは仕方ないです(笑)
フレンチトーストがうまく焼けるようになるまでのシングル・ファーザーと子供の一年半の物語の映画は、吉本センセのような事情ではなくて、極めて現代的な光景です。
1960年代からウーマン・リブ(今では「フェミニズム」)の運動が盛んになったのは、同時代のマイノリティたちの権利拡大の流れのひとつに位置づけられます。黒人・同性愛者・女性・少数民族・新興宗教・平和主義等々の少数派だった人々の主張は、70年代になってから一挙に開花することになります。
もちろん、これらによからぬ思いを抱く人間もいるでしょう。実際、社会の秩序や宗教観に対するアンチなわけですから。
ちょっと思い出しましょう。「タクシードライバー」「ロッキー」「猿の惑星」、皆これかなりの黒人「差別」の映画です。黒人の権利拡大とブラックパワーの高揚は、これに対するアンチの映画をつくりあげました。ただし、ここで「差別」とカッコ付きにしたのは、黒人を差別を撤廃したことにより、もともと差別する側だった人間(白人)が窮屈な思いをしているという認識から来ているためです。むしろ彼らは逆差別されていると思い込んでいるわけです。
法律も逆差別されている人には味方ではない。「ダーティーハリー」は法律がむしろ悪を野放しにする手助けをしているという、極めて危険な思想に基づいた映画でした。ただし、この映画は、正しいはずの法律が逆に抑圧されている人々を生み出しているやりきれなさをうまくカタルシスに昇華させています。
そんなわけで、この映画もそういうアンチ70年代の映画にカテゴライズされていいと思います。ウーマンリブやフェミニズムへの反撃なわけです。
給料もよろしい、妻に手を上げられるようなこともない、ちょっと仕事に忙しくて家のことを省みない。だけど、妻は何かに不満をもって出て行ってしまう。性的なことだったらクレイマーvsクレイマーの裁判の中で触れられるでしょう。(欧米はそういうところですよ)
人生にふと疑問を感じたのか、ウーマンリブの友達にそそのかされたのか、妻は不条理なまでに、いきなり家出。
そして働きだせばダンナと給料もあんまり変わらないくらいのいい稼ぎだったりもするわけです。離婚裁判で養育権を巡れば、もうほとんど男性に勝ち目はありません。これは日本もアメリカも同じ。母親の方が養育にはよいという判断なのです。
しかし!ここで出てくるのが「男の本質・マザーシップ」の発現なわけです(笑)
なんというか、すごいウーマンリブへの反撃です。それに最後は母親も負けてしまうわけです。いやはやなんとも(笑)
ウーマンリブへの異議申し立ての映画が、ここまで面白おかしくできたのは、やっぱりダスティン・ホフマンであるからなんでしょうね。当時流行りだした言葉でいえば「ヤッピー」調の仕事命の男のマザーシップへの回帰。なるほど面白い映画です。
1979年の映画ですか。自立した強い女が性的メタファーの中で戦い続ける「エイリアン」もこの年ですね。エイリアンかダスティン・ホフマンのマザーシップが、アンチ・ウーマンリブの凱歌をあげていた時代ということですかね。
みゆき座「午前十時の映画祭にて」
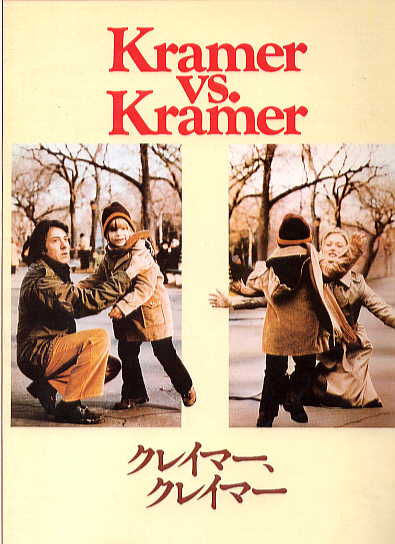
コメント